2人目の赤ちゃんが生まれると、生活リズムも家族の関係性も大きく変わります。
とくに寝室のレイアウトは、上の子との関係や夜のお世話のしやすさに直結する重要ポイント。
夜泣き・添い寝・安全対策など、あらかじめ考えておきたいことがたくさんあります。
この記事では、家族みんなが快適に過ごせる寝室づくりのヒントを、実体験を交えながらご紹介します。
2人目が生まれる前に考えたい、寝室レイアウトの見直し

2人目の赤ちゃんが無事に誕生し、やっとひと息……と思ったのも束の間。
病院から戻っていざ一緒に寝ることになると、昼夜の区別がついていない新生児は、夜中に突然泣き出すことも。
どんなに授乳しても泣き止まないと、「あぁ、そうだった……赤ちゃんってこんな感じだった」と、ふと我に返る瞬間があるんですよね。
私が直面したのは、当時4歳だった上の子と、生まれたばかりの赤ちゃんを同じ部屋で寝かせることができるのか?という新たな不安でした。
上の子の赤ちゃん返りもあって、思っていたよりもずっとバタバタの毎日。
その中で、
- 「赤ちゃんをどこで寝かせるか」
- 「ベビーベッドにする?お布団がいい?」
といった寝室のレイアウトについて、改めて見直すことになりました。
これからベビーベッドを用意しようか迷っている方や、部屋の使い方を工夫したいと考えている方のヒントになればうれしいです。
赤ちゃんを寝かせる場所は「昼」と「夜」で変えるのがベスト
いろいろ調べてみたところ、昼間は約7割のママが赤ちゃんをリビングで過ごさせていることがわかりました。
私自身もそうでした。朝起きてから夜寝るまで、ほとんどの時間を赤ちゃんと一緒にリビングで過ごしていたんです。家事の合間に様子が見やすく、何かと安心できる空間でした。
夜になると、今度は9割近くのママが赤ちゃんを寝室で寝かせているという調査結果も。
家族と過ごす空間と、赤ちゃんがゆったり眠れる空間をうまく分けることで、生活リズムが整いやすくなるのかもしれませんね。
昼間はリビングが基本・部屋づくりのポイント

1人目のときは、静かなリビングに布団を敷いて赤ちゃんを寝かせていたという方も多いのではないでしょうか。
周りにいるのは大人だけなので、それほど心配することもなかったと思います。
けれども2人目となると事情が変わってきます。
上の子がまだ小さいと、じっとしていてくれるわけではないですし、赤ちゃんの安全をどう守るかという視点も必要になってきます。
「どうやったら赤ちゃんを安全に寝かせられるだろう?」「上の子と過ごす時間も大切にしながら、赤ちゃんのお世話はできるかな?」と、いろいろ調べたり工夫したりしました。
踏まれたり、いじられたり!?上の子と赤ちゃんの安全な距離感を考えよう
2人目育児で最初に直面したのは、「上の子が赤ちゃんにちょっかいを出しすぎないか?」という心配でした。
赤ちゃんを床に寝かせると…
- 上の子が無意識に近づいてきて、うっかり踏んでしまうかも
- 赤ちゃんの真似をして、口に物を入れてしまうかも
- お布団をかけてくれるつもりが、顔まで覆ってしまうことも…
など、思わぬトラブルのもとになってしまいます。
そのため、わが家ではリビングでもベビーベッドを使うようにして、赤ちゃんを少し高い位置に寝かせることで事故のリスクを減らしました。
上の子には「ここは赤ちゃんの場所だよ」と少しずつ理解してもらうようにしたんです。
【誤飲に注意!】上の子のおもちゃは“要管理”
赤ちゃんは、興味のあるものにすぐ手を伸ばします。そして手に取ったものは、なんでもお口に入れたくなる時期がありますよね。
特に注意したいのが、小さなおもちゃや文具類です。
たとえば…
鉛筆・クレヨンやその削りかす
シールやステッカーの切れ端
消しゴムのかけらや文具のキャップ
小さなフィギュアやガチャガチャのおもちゃ
ゼムクリップや輪ゴム
これらは、直径4cm以下のものであれば誤って飲み込んでしまう可能性があるため、赤ちゃんのそばに置かないように気をつけましょう。
上の子の遊びスペースと赤ちゃんのスペースはきちんと分ける、もしくは上の子のおもちゃは専用のボックスに入れて片付けるなどの工夫がおすすめです。
お世話グッズの管理にも一工夫を
赤ちゃんの爪切りや綿棒、体温計やクリームなどのお世話グッズは、ママにとってはすぐ手の届く場所にあると便利です。
でも、上の子がいるとそうもいきません。
「ママが赤ちゃんのお世話してる!私もやってあげたい!」という気持ちはとても可愛いのですが、綿棒を持って鼻をほじろうとしたり、爪切りを持って赤ちゃんの指に向かおうとしたり……ヒヤッとする場面も。
こうした道具は、小さい子の目につかない・手の届かない場所に収納するようにした方が安心です。
ちょっと手間が増えるかもしれませんが、安全のためにはとても大切な工夫になりますよ。
昼間のリビング・赤ちゃんが心地よく過ごせる環境づくりとは?

赤ちゃん専用の「安心できる寝場所」をつくろう
お兄ちゃん・お姉ちゃんが元気に走り回るリビングでは、赤ちゃんの寝るスペースも工夫が必要になります。
そんなときに役立つのが、ベビーベッドやハイローチェアなど、床から少し高さのある寝かせグッズ。
これなら、万が一上の子が近くで遊んでいても、赤ちゃんが踏まれてしまう心配が減ります。
また、高さのある場所は床のほこりも舞いにくく、赤ちゃんにとっても衛生的なんです。
ベビーベッドは使える時期が限られていて、長く使うわけではないので、レンタルという選択はスペースを節約したいご家庭にもぴったりです。
設置する際は、
- 照明のまぶしさが直接届かない場所
- エアコンの風が当たらない位置
- 物が上から落ちてこないところ
- 家事の合間でも赤ちゃんの様子が目に入る場所
などを意識して選ぶと安心ですよ。
お世話グッズは「使いやすく、かつ安全に」収納するのがコツ
オムツ替えや吐き戻しのときなど、赤ちゃんのお世話はすぐに対応が必要なことが多いですよね。
オムツやおしりふき、ガーゼや着替え、保湿クリームや綿棒、爪切りといったケアアイテムは、「手が届く場所にすぐ取れる」ようにまとめておくと、とてもスムーズです。
ただし、上の子がまだ小さいときは注意も必要。
好奇心いっぱいで「やってみたい!」という気持ちから、ママのお手伝いをしてくれるつもりで、ケアグッズをさわってしまうことも。
安全のためにも、赤ちゃんグッズは高い位置に、分類して整理しておくのがおすすめです。
また、収納棚の下にベビーベッドを置いてしまうと、万が一の落下事故が起きるおそれがあります。
赤ちゃんの上に物が落ちないように、置き場所にも気をつけてあげましょう。
夜の寝室・上の子と赤ちゃん、どこでどう寝る?2人目が生まれた後のレイアウト

赤ちゃんの寝床はママのすぐそばが安心
夜、赤ちゃんを寝かせる場所としておすすめなのは、言うまでもなくママのすぐ近く。
たとえば、ママがベッドで寝ているなら、ベビーベッドを横に並べて置くスタイルが便利です。
同じくらいの高さに合わせれば、夜中に赤ちゃんの様子を確認したり、授乳したりするのもグッとラクになります。
わが家では、下の子が生まれる前は親子3人で川の字になってベッドで寝ていたのですが、レイアウトを変えました。
ベビーベッドを追加することで赤ちゃん専用の安心スペースができて、とても助かりました。
一方で、赤ちゃんをママのベッドに寝かせる「添い寝」スタイルにするなら、ベッドからの落下を防ぐためのガードは必ず設置して、安全面に配慮してくださいね。
夜中のお世話はし辛いですが、ベビーベッドで高さを出すことで、親の布団が赤ちゃんの方に行ってしまって…というリスクを減らせます。
添い寝でぐっすり?布団スタイルも柔軟に
赤ちゃんのなかには、ベビーベッドだとうまく眠れなかったり、ママのぬくもりがそばにないと泣いてしまう子もいます。
そんなときは、ママの布団のすぐ横に赤ちゃん用のお布団を敷いて添い寝してあげるのもひとつの方法です。
特に新生児の時期は、授乳にオムツ替え、寝かしつけとお世話がつづくので、少しでもママが体を休められるようなスタイルを選ぶことが大切です。
添い乳がしやすくなることで、寝かしつけもスムーズになるかもしれません。
ただし、布団の場合は上の子との距離にも気をつけましょう。
寝相が悪かったり、夜中に動き回ることもあるので、赤ちゃんの周りにもう一枚布団を敷いたり、少し離して寝かせたりと、ちょっとした工夫が必要です。
上の子の眠りも大切に
赤ちゃんのお世話が始まると、どうしても生活の中心は下の子になりがち。
わが家では、夜は家族みんなで布団を並べて寝るスタイル。パパ、上の子、私、そして赤ちゃんという順番で寝ていました。
ただ、最初の1〜2ヶ月は赤ちゃんがまだ生活リズムをつかめず、夜中に泣くことも多く、上の子の眠りが浅くなったり、寝不足になったりすることもありました。
さらに、日中は保育園で頑張っている上の子が「寂しい」と感じている様子も見えてきて、精神的なケアの必要性も感じるように…。
そこで私は、赤ちゃんの寝かしつけは一時的に夫や実家の母にお願いして、上の子と過ごす時間を意識的に増やすようにしました。
絵本を読んだり、「今日はどうだった?」とゆっくりお話したり。
赤ちゃんがいても「自分は大切にされている」と感じてもらえる時間をつくることが、安心して眠れる環境づくりにもつながったように思います。
上の子が寝たら、赤ちゃんタイムにシフト!短時間でも仮眠を確保
赤ちゃんが生後3〜4ヶ月になる頃には、夜のリズムもだんだん落ち着いてくる(個人差あり、我が家の1人目は1年は不規則だった…)傾向が。
そのころまでは、毎晩「上の子が眠ってから、赤ちゃんのお世話を始める」という流れを続けていました。
ときには、パパと上の子だけ先に寝てもらって、私は赤ちゃんの授乳までのあいだにサッと仮眠を取る、なんていう工夫も。
もちろんパパの仕事の時間や生活リズムもあるので、毎日が完璧にいくわけではありません。
でも、家族で協力しながら“みんなが少しずつ眠れる形”を模索していくことが大切だなと実感しました。
完璧じゃなくて大丈夫。その日そのときに合った寝方を
事前にしっかり準備していても、いざ赤ちゃんが生まれてみると「思ってたのと違う…」ということもたくさんあります。
寝室のレイアウトは、赤ちゃんの性格やその日の様子に合わせて調整するのがコツです。
「これじゃないとダメ」と決めすぎず、「今日はこうしてみようかな」と柔軟に対応できると、ママも赤ちゃんもきっとラクになりますよ。
ちなみに、夜の寝かせ方については「ベビーベッドがいいのか、布団がいいのか」などもいろいろと調べました。
それぞれにメリット・デメリットはあるので、生活スタイルや寝室の広さ、上の子との関係性に合わせて選んでいくといいですね。
ベビーベッド?布団?それぞれの良さと気をつけたい点を比べてみる

赤ちゃんの寝かせ方については、ご家庭の環境や赤ちゃんの性格、上の子の有無によっても選び方が変わってきますよね。
「どれが正解」ということはなく、それぞれに良いところもあれば気をつけるポイントもあります。
以下の表で、それぞれの特徴をわかりやすく比較してみました。
赤ちゃんの寝かせ方 比較表
| 寝かせ方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ベビーベッド | ・赤ちゃんの安全を守れる ・おむつ替えの姿勢が楽 ・ホコリを避けやすい ・ベビーゲージとしても活用可能 |
・場所を取る ・価格がやや高め ・添い寝がしにくい ・夜泣き対応に移動が必要な場合も |
| ベビー布団 | ・持ち運びしやすい ・場所を選ばず使える ・赤ちゃんにフィットしやすい ・添い寝もしやすい |
・床近くなのでホコリが気になる ・高さがないため腰に負担がかかることも ・就学前までの使用が目安 ・上の子が踏んでしまう可能性あり |
| 親と一緒の布団・ベッド | ・添い寝ができて安心感がある ・夜中の対応がすぐできる ・別途寝具を用意しなくていい |
・寝返りなどで赤ちゃんを圧迫する危険がある ・ベッドだと落下のリスクあり ・大人用の布団が顔にかかる心配も |
「赤ちゃんにとって」「家族にとって」「ママにとって」ちょうど良いバランスを探しながら、柔軟に選んでいけるといいですね。
まとめ|2人目が生まれたあとの寝室レイアウトは柔軟さがカギ!
2人目の寝室レイアウトには、赤ちゃんの性格や上の子の年齢、家庭のスペース事情など、さまざまな要素が関わります。
完璧な正解はありませんが、「安全性」「見守りやすさ」「家族全員の快眠」を軸に、柔軟に工夫していくことがポイントです。
最後に、寝かせ方別のメリット・デメリットを再確認しましょう。
| 寝かせ方 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|
| ベビーベッド | 安全性が高く、ホコリ対策になる | 場所を取る、添い寝しづらい |
| ベビー布団 | 持ち運びがしやすく柔軟に使える | 床が近くてホコリが心配 |
| 一緒の布団・ベッド | 添い寝で安心感あり | 圧迫や落下などのリスクあり |

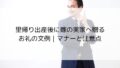
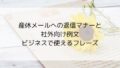
コメント