書類不備のお詫びや送付状は、ビジネスの信頼関係を保つうえでとても大切な対応です。
ほんの小さな抜けや誤記でも、相手の業務に支障をきたしてしまうことがあります。
この記事では
- 書類不備のお詫びが必要な理由
- 送付状の基本構成と書き方のポイント
- 実際に使える例文集
をわかりやすく解説します。
最後まで読むことで、不備が起きたときにも落ち着いて対応できるようになりますよ。
書類不備のお詫びが必要な理由とは【マナーの確認】

よくある書類不備のケースと背景
ビジネスの現場では、ほんのわずかなミスでも、大きなトラブルや誤解を生んでしまうことがあります。
書類に関していえば、特に見落とされがちなのが、記載項目の抜けや名前・日付の誤記、添付資料の入れ忘れなどです。
たとえば、契約書に捺印がなかったり、見積書の日付が古いままだったりすることがあります。
また、必要な書類がそもそも同封されていなかったというケースも少なくありません。
これらの不備は、たいていは
- 「うっかり」
- 「急ぎすぎたため」
に起こります。 ただ、どんな理由があるにせよ、受け取った相手にとっては業務が進まない原因となり、場合によっては社内稟議が止まってしまうなどの影響もあります。
特に初めてやり取りをする相手や、重要な書類をやり取りしている場合には、より慎重な対応が求められます。
相手への影響と信頼への影響
書類の不備がもたらす影響は、単に再提出の手間をかけるということにとどまりません。
相手は本来不要な確認作業や対応に時間を取られることになりますし、その間に本来の業務が後ろ倒しになることもあります。
以下に、不備によって相手に生じる主な影響を表で整理しました。
| 影響の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 作業の手間 | 本来不要だった再確認、再処理、担当者間のやり取りが必要になる |
| 業務スケジュールの遅れ | 書類の不備によって承認フローや納期などがずれ込む可能性がある |
| 精神的な負担 | 「またかもしれない」という不安が積み重なり、相手の信頼感が薄れる |
また、一度でも不備があると「また同じことが起こるのでは」と思われるようになり、やり取り全体に慎重さが加わります。
それが積み重なることで、結果として信頼感が薄れてしまうリスクもあります。
丁寧なお詫びと、何よりもスピーディーな再送・再対応を行うことが、信頼を取り戻す第一歩です。
その場限りのやり過ごしではなく、次につなげる対応が求められます。
書類不備に対するお詫び文の基本構成

謝罪・原因説明・再送案内の流れ
そのためには、次の3つの要素を丁寧に盛り込むのが基本です。
- 不備についての謝罪(最初に一言で述べると印象が柔らかくなります)
- 発生した原因の説明(必要以上に詳細にはせず、簡潔かつ納得感のある内容に)
- 正しい書類の再送または補足対応の案内(再発防止の意思を感じさせるとより丁寧)
たとえば、「このたびお送りした書類に一部不足がございましたことをお詫び申し上げます」から始め、 「確認不足により添付書類が同封されておりませんでした」など、具体的に説明すると相手も状況を把握しやすくなります。
そのうえで、「必要書類を改めて本日中に送付させていただきます」など、対応の予定や方法をしっかり伝えましょう。
一文ごとに区切りながら丁寧に書くことで、読み手にとっても負担の少ない文章になります。
誠意が伝わる表現のコツ
誠実な印象を持ってもらうためには、定型の言葉をそのまま使うよりも、少し言い回しを変えて気持ちが伝わるように工夫するのがおすすめです。
たとえば「お手数をおかけして申し訳ございませんでした」という表現も丁寧ですが、
- 「お手間を取らせてしまい、心よりお詫び申し上げます」
- 「ご面倒をおかけしましたこと、深くお詫びいたします」
など、 相手の立場を思いやった言葉にするだけで、ぐっと印象が変わります。
また、文末に「今後はこのようなことのないよう、確認体制を整えてまいります」といった一言を加えることで、 誠意と前向きな姿勢が伝わりやすくなります。
形式だけにとらわれず、相手に寄り添う姿勢を意識して書くことが、信頼回復への第一歩です。
送付状の書き方と記載すべき項目

送付状に必要な基本要素とは
送付状は、添付書類の内容や目的を受け取り手に正しく伝えるための大切な書面です。
形式ばった印象になりがちですが、伝えるべきポイントを押さえたうえで、丁寧な言葉を選ぶことによって、相手に良い印象を与えることもできます。
まず、送付状には
- 「誰から」
- 「誰へ」
- 「何を」
- 「なぜ」
送るのかが明確にわかるように記載することが大切です。
また、書類の不備に対するお詫びや今後の対応についても簡潔に添えておくと、相手も状況を理解しやすくなります。
以下の項目は基本として押さえておきましょう。
- 相手の会社名・部署名・氏名(敬称も含めて丁寧に)
- 自分の会社名、部署、氏名、連絡先
- 送付する書類の概要(例:請求書一式、契約書控えなど)
- 不備があったことへのお詫びの一文と、再送の旨
- 今後の対応予定や補足事項(必要に応じて)
- 結びのあいさつ(感謝の気持ちや今後のお付き合いに関するひと言)
また、送付状は堅苦しくなりすぎないように、行間をゆったりと取る、文末に季節の挨拶を添えるといった工夫も好印象につながります。
テンプレートを活用する方法
最近では、WordやGoogleドキュメントにあらかじめ整ったフォーマットが用意されていることもあります。
ただし、テンプレートをそのまま使用するのではなく、実際のやり取りや相手との関係性に合わせて文面を調整することがポイントです。
たとえば、
- ややカジュアルな相手先には定型的な敬語を柔らかくする
- 以前からのやり取りがある場合は「いつもお世話になっております」といったひと言を添える
など、気配りを加えることで印象が変わります。
一度自分の型を作ってしまえば、次回以降はそれをベースに調整して使えるため、手間を減らしながらも丁寧な対応が可能になります。
書類の送付方法とマナー

郵送とメールの使い分け方
書類を送る際は、相手との関係性や書類の内容、重要度などを踏まえて、適切な送付手段を選ぶことが大切です。
送付方法ひとつで、相手に与える印象や対応のしやすさが大きく変わってきます。
- 原本のやり取りや署名が必要な契約書類など、正式性が求められる場合:郵送(書留や簡易書留、レターパックなど)
- 再発行が難しい証明書類や控えの返送が必要なもの:郵送が無難
- 修正済みのデータファイルや案内状など、簡易なやり取り:メールに添付して送信
また、急ぎの場合は、まずメールで内容を送り、その後原本を郵送するという併用も一つの方法です。
特に初回のやり取りでは郵送を基本とし、やり取りに慣れてきたらメールへ移行するのも選択肢です。
状況ごとに「どちらが適しているか」を都度見極める柔軟な判断が求められます。
件名や送付タイミングの注意点
メールを使う際には、件名で要件がすぐ伝わるように工夫すると、相手にとって親切です。
たとえば以下のような件名例があります。
- 書類再送のお知らせ(お詫び)
- 【再送】〇〇書類について
- 【重要】再送書類のご確認をお願いいたします
また、送信するタイミングも重要です。
可能であれば不備が判明した時点ですぐに対応し、その日のうちに再送するのがベストです。
遅くとも翌営業日中には送付完了しておくことで、相手に不安を与えにくくなります。
再送メールには本文でも「早急に対応した旨」「再発防止への配慮」など、ひとこと添えると丁寧な印象になります。
書類不備を防ぐためのチェックポイント

再発防止の体制づくりとチェック方法
単発のミスは誰にでも起こり得ますが、仕組みとして再発を防ぐ工夫を組み込んでおくことが重要です。
以下のような対策が効果的です。
- ダブルチェックのルールを設ける: 一人で完結させず、必ず他の人の目を通すようにすることで、見落としのリスクを減らせます。 特に重要書類の場合は、複数人で内容・日付・添付物を確認する体制が有効です。
- チェックリストを活用する: 書類の種類ごとに必要項目をまとめたチェックリストを作成し、作業の都度確認する運用にすると、不備の見逃しを防げます。 印刷やPDF化のタイミングで、一覧にチェックを入れるルールにしておくのもおすすめです。
- 送付前に一呼吸おいて確認する習慣をつける: 急いでいるときほどミスは起きやすいもの。 書類を封入・送信する前に、数分でいいので深呼吸して見直す時間を取るだけで、大きな違いが生まれます。 見慣れた書類ほど注意が必要です。
- トラブル事例の共有を習慣にする: 小さなミスや過去の不備の事例をチーム内で共有しておくと、同じミスの再発を防ぐ効果があります。 月に一度の振り返りミーティングなどで定期的に扱うと、意識づけにもつながります。
こうした小さな取り組みの積み重ねが、ミスを未然に防ぐ大きな力となります。
また、個人ではなくチーム全体で取り組む意識を持つことで、チェック体制の質も安定していきます。
書類不備のお詫び・送付状の文例集

謝罪文の例(再送連絡含む)
例文①
このたびは、弊社よりお送りいたしました書類に不備があり、ご迷惑とお手間をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。 内容を再度確認いたしましたところ、一部に記載漏れがあったことが判明いたしました。 本来であれば、十分な確認のうえでお届けすべきところ、結果的にお時間を頂戴してしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
つきましては、修正済みの正しい書類を改めて本日付で発送させていただきました。 お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
今後はこのようなことのないよう、書類作成から送付までの工程を見直し、再発防止に努めてまいります。 引き続き変わらぬご指導とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
例文②
このたびお届けいたしました書類に、誤りがございましたことを心よりお詫び申し上げます。 弊社の確認不足により、一部内容に誤記が含まれておりました。 業務のお手を煩わせてしまい、誠に申し訳ございません。
ただいま、修正済みの書類を再度お送りしておりますので、お手数ではございますがご確認くださいますようお願い申し上げます。 今後は同様のことが起こらぬよう、社内チェック体制の見直しを行ってまいります。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
例文③
お送りいたしました書類に不備がありましたこと、まずは深くお詫び申し上げます。 内容を確認したところ、必要な添付資料が同封されておりませんでした。 確認が行き届いておらず、ご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。
至急、該当資料を追って郵送いたします。 お手元に届きましたら、お手数ですがご確認いただけますと幸いです。
再発防止に向け、今後は社内のフローを見直し、チェック体制の強化に努めてまいります。 引き続き変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。
送付状の例(添え文付き)
例文①
拝啓 残暑厳しき折、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先日お送りいたしました書類に一部不備がございました件につきまして、心よりお詫び申し上げます。 本日、正しい内容に修正した書類を再度同封いたしましたので、恐れ入りますがご確認くださいますようお願い申し上げます。
今後は同様の事態を防ぐべく、社内確認体制の強化に努めてまいります。 末筆ながら、皆様のご健勝と貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。
敬具
例文②
拝啓 初秋の候、貴社におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたびお届けいたしました書類に内容の誤りがございましたこと、深くお詫び申し上げます。 誤記のあった箇所を修正し、正しい書類を同封のうえ再送いたしますので、何卒ご確認いただけますようお願い申し上げます。
今後はこのようなことがないよう、確認体制を見直してまいります。 引き続きのご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
敬具
例文③
拝啓 秋涼の候、貴社益々ご繁栄のことと心よりお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
先日お送りいたしました書類に添付漏れがございました件につきまして、ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。 つきましては、不足しておりました資料を同封し、再送いたしますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
今後は社内体制を見直し、より一層の確認を徹底してまいります。 変わらぬご厚誼のほど、お願い申し上げます。
敬具
まとめ
書類不備は相手の作業を増やすだけでなく、信頼低下にもつながります。
だからこそ、お詫びの言葉と迅速な対応が欠かせません。
送付状には基本の構成を押さえ、誠意ある表現を添えることで、相手に安心して受け取ってもらえます。
最後にポイントを表にまとめました。
| ポイント | 具体例 |
|---|---|
| 謝罪の一文 | このたびは不備があり申し訳ございません |
| 原因の簡潔な説明 | 添付資料が不足しておりました |
| 再送・対応の案内 | 修正済みの書類を本日再送いたします |
| 再発防止の意思 | 確認体制を見直してまいります |
誠意が伝わる文面を意識し、今後の関係をより良いものにしていきましょう。

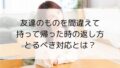
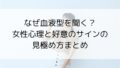
コメント