メールが届いていないと連絡を受けたとき、焦ってしまう方は多いのではないでしょうか。
再送の際には、ただ送り直すだけでなく、丁寧なお詫びや確認が必要です。この記事では、以下の内容をわかりやすく解説します。
- 再送前に確認すべきチェックポイント
- お詫びと再送を両立させる文章のコツ
- 取引先・上司・同僚向けの再送メール例文
最後まで読むことで、相手に配慮が伝わるメール対応ができるようになります。
メールが届いていないと連絡を受けた時の初動対応

まず確認すべき3つのポイントと返信マナー
相手から「メールが届いていない」と連絡をもらったとき、焦ってしまう気持ちはよくわかりますが、まずは冷静に状況を把握することが大切です。
以下の3つのチェックポイントを順に確認しましょう。
- 送信先アドレスに打ち間違いがないか(全角・半角の混在にも注意)
- 添付ファイルが大きすぎたり、特殊な形式になっていないか
- 相手の迷惑メールフォルダやプロモーションタブに振り分けられていないか
とくに、社外への初回送信などでは、メールフィルターに引っかかってしまうケースも見受けられます。
また、あらためてご連絡をいただいたことに対して、「気づかせてくれてありがとう」という感謝の気持ちを最初に添えると、やり取りがぐっと円滑になります。
再送メールは単なる情報の再提示ではなく、相手との信頼関係を保つための大切なコミュニケーションです。
だからこそ、少しの気配りを忘れずに、丁寧に対応することが求められます。
メールが本当に届いていないか確認する方法
再送の前に、こちら側の送信状態を再確認しておくと、同じ状況を繰り返さずに済みます。
具体的には、次のような点に目を向けてみましょう。
- 送信済みフォルダに残っているか(誤って保存のみになっていないか)
- 自動返信でエラー通知(バウンスメール)が届いていないか
- 他の宛先には届いているか、CCの人から返事がきていないか
可能であれば、社内のIT部門やシステム管理者にサーバーの状況を確認してもらうのもおすすめです。
ごくまれに一時的な通信障害やメーリングシステムの設定変更によって、正常に送信されたはずのメールが届かないこともあります。
こうした確認を丁寧に行うことで、再送の際に相手に対して適切な説明ができ、誠意ある対応として受け取ってもらいやすくなります。
再送メールを送る際の基本マナーと注意点

イミング・送信先・送信方法のチェック
まずは一呼吸おいて、再送の前に内容や送信環境の確認をしっかり行いましょう。
急ぎの要件であっても、慌てず丁寧に対応することが結果として相手への信頼につながります。
再送メールの前に確認すべき項目を以下にまとめました。
| 確認項目 | 内容の説明 |
|---|---|
| 内容の確認 | 前回と同じ文面でよいか、誤字脱字や記載漏れがないかをチェック |
| 添付ファイルの確認 | 添付し忘れ、形式の違い、容量オーバーがないか |
| メールアドレスの確認 | 宛先に誤りがないか(全角・半角含め) |
| 通信環境の確認 | 自分の送信環境が正常か、サーバーエラーなどが発生していないか |
| メール形式や署名の確認 | HTMLメールとテキストメールの使い分け、署名の有無 |
送信先が複数ある場合、他の方には届いていたのかどうかも確認することで、単なるアドレスの入力ミスや一部のドメインでの不達など、原因の切り分けにも役立ちます。
また、メーリングリストやCCに含まれていた方の返信状況などから、全体の届き具合を推測する手がかりにもなるでしょう。
さらに、前回と同じ方法で送信してもまた届かない可能性があります。
そのため、場合によっては電話やチャットツールなど、別の連絡手段を併用することも視野に入れておくと安心です。
特に重要な資料や期日が迫っている場合は、相手に確実に届いていることを確認できる手段を選ぶことがポイントです。
メールに頼らず、相手に届いたことを直接確認できる手段を持つことは、ビジネス上のリスク管理としても有効です。
再送時の宛名・CC・BCCの設定ミスを防ぐチェックポイント
再送する際には、つい慣れから確認を怠ってしまうことがありますが、細かな部分にこそ注意が必要です。
特に以下の3点は再送時によく起こりやすいミスです。
- 敬称の付け忘れや誤記:特に名前を入力し直した場合などに注意が必要です。
- BCCとCCの入れ違い:意図しない人に情報が見えてしまうことのないよう、設定は慎重に確認しましょう。
- 前回と同じ宛先かどうかの再確認:うっかり違うアドレスに送ってしまうミスを防ぐためにも、履歴だけに頼らず再入力や目視確認を心がけてください。
一見小さなことのように思えても、ビジネスメールでは信頼性が問われる大切な要素です。
再送だからこそ、相手への配慮を忘れず、丁寧な確認を心がけることで、より誠実な対応につながります。
再送メールの構成と書き方のポイント

件名・本文・添付の記載ルールまとめ
再送メールの件名は、相手に気づいてもらいやすくするためにひと工夫が必要です。
ただ「○○の件」では見逃される可能性があるため、再送であることをはっきり示すようにしましょう。
たとえば、
- 【再送】○○のご連絡
- ○○の件(再送)
- ○○資料の再送について
など、件名の先頭や末尾に「再送」の文字を含めることで、受信者の目に留まりやすくなります。
可能であれば、初回送信時の件名を維持しつつ再送の旨を加えると、相手も内容を把握しやすくなります。
本文では、まず再送に至った経緯を簡潔に述べましょう。
例として「先ほどのメールが届いていない可能性があるため、念のため再送いたします」といった導入文を入れることで、丁寧な印象を与えることができます。
その後は、要点を整理し、読みやすい形で情報を記載します。 箇条書きや段落分けを活用すると、より伝わりやすくなります。
添付ファイルがある場合は、ファイル名だけでなく内容の概要や目的についても一言添えておくと親切です。
たとえば、「こちらが○○のご提案資料になります」といったように一文添えるだけで、受信者はスムーズに内容を理解できます。
ファイルが複数ある場合は、番号や順序、補足説明を入れておくとより親切です。
お詫びと再送の文面を両立させる文章構成のコツ
お詫びの言葉を入れることは大切ですが、過度に恐縮しすぎず、相手が構えずに読める雰囲気づくりも必要です。
たとえば、
- お手数をおかけして申し訳ありません
- 念のため、再送させていただきます
- ご確認いただけるよう再送いたします
など、控えめでやさしい表現を選ぶことで、柔らかい印象を与えることができます。
また、再送は必ずしもミスやトラブルが原因とは限りません。
通信環境やメールの振り分け設定など、さまざまな要因が考えられるため、再送=謝罪という前提になりすぎないよう気をつけましょう。
文末には「ご不明点等ございましたら、お知らせいただけますと幸いです」などのフォロー文を添えることで、丁寧な印象とともにやり取りの継続を促すことができます。
お詫び表現の選び方|丁寧で伝わる言い回し

クッション言葉の工夫と活用例
文章の印象をやわらげたり、唐突さを避けたりするのに役立つのが「クッション言葉」です。
特にビジネスメールにおいては、直接的な表現を避けつつ、相手に配慮を伝える手段として重宝されます。
以下のような言い回しがよく使われます。
- ご多忙のところ恐れ入りますが
- 失礼かと存じますが
- 念のためのご連絡となりますが
- お手間を取らせてしまい恐縮ですが
- 差し支えなければ
これらを文章の冒頭や要件に入る前に一言添えることで、柔らかな印象になり、相手も内容を受け取りやすくなります。
また、クッション言葉は単に丁寧に見せるだけでなく、「あなたを尊重しています」という気持ちを表現するツールでもあります。
例えば、再送メールであれば、 「念のためのご連絡となりますが、前回のメールが届いていない可能性があるため…」 というように前置きすることで、再送が押しつけがましくならず、やさしい印象に変わります。
「再送いたします」の自然な使い方
「再送いたします」は再送メールの定番フレーズですが、連続して使うと事務的に見えてしまうこともあります。
相手との関係性や文脈によって、表現に少し変化をつけると、より読みやすく、やわらかい印象になります。
たとえば以下のような表現が効果的です。
- 改めてご送付いたします
- ご確認いただけるよう、再度お送りします
- 念のため、再度お届けさせていただきます
- もう一度お送りいたしますので、ご確認くださいませ
どの表現も相手に負担をかけず、さりげない配慮を感じさせる言い回しです。
受け取り手が「丁寧だな」と感じる小さな工夫が、やりとり全体の雰囲気を和やかにします。
「ご確認いただけますと幸いです」などの柔らかい表現集
だからこそ、強制感のない、やわらかい表現を選ぶことが大切です。
以下は使いやすく、丁寧さと配慮が感じられる表現の例です。
- お手すきの際にご覧いただけましたら嬉しいです
- ご都合のよろしい時にご確認いただければと思います
- 内容に不備等ございましたら、お知らせいただけますと助かります
- ご確認いただけるとありがたく存じます
- 何かご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお申しつけください
これらの表現は、受け手に優しい印象を与えるだけでなく、やり取りを継続しやすくするという利点もあります。
メール本文に丁寧なクッションと言葉の温度感を加えることで、スムーズなコミュニケーションが実現します。
「メールが届いていない」と言われたときのお詫び再送メールの例文【相手別】

取引先・上司・社内向けの例文パターン
それぞれの立場に応じて、文面のトーンや言葉選びを丁寧に調整することが、良好なコミュニケーションを保つコツです。
一見同じ「再送メール」であっても、受け取る相手の役職や関係性によって、印象は大きく変わってきます。
【取引先向け①】
【取引先向け②】
【取引先向け③】
【上司向け①】
【上司向け②】
【上司向け③】
【社内同僚向け①】
【社内同僚向け②】
【社内同僚向け③】
それぞれの文例では、「形式的すぎず、かつ失礼にならない」絶妙なバランスがポイントです。
取引先には丁寧で誠実な姿勢を、上司には信頼と配慮を、同僚には柔らかく自然な距離感を意識しましょう。
再送後の確認とトラブル予防

二重送信や誤送信を防ぐちょっとした工夫
- 添付ファイルの内容と件名が一致しているか
- 古いメールスレッドを使い回していないか
- 送信前に一度下書き保存して見直す
- メール本文と添付資料の関連性がきちんとあるか再確認する
- 誤変換や敬称間違いなど、細かな文言を見落としていないかチェック
こうした小さな確認作業を習慣づけることで、うっかりミスや不本意な誤送信を未然に防ぐことができます。
また、送信前に「テスト送信用の自分宛メール」を一度送って確認する方法も有効です。
メールが意図したとおりの表示になっているか、誤解を招くような表現がないかを、客観的に見直すことができるからです。
時間に追われていると、つい確認を省いてしまいがちですが、その数分の見直しが、のちの大きな信頼損失を防ぐ一手になります。
大切なやりとりほど、念入りな確認を心がけるようにしましょう。
再送後のフォローで信頼を保つ方法
再送したあと、相手からの返信が届いたかどうかを確認するのはもちろん、返信が遅れている場合でも、すぐに催促せず少し待つことも大切です。
また、再送後に直接顔を合わせる機会があるなら、口頭で「先ほどメールを再送しましたので、よろしくお願いします」といった一言を添えると、より丁寧な印象になります。
重要な要件であるなら、電話を入れるのも選択肢の一つです。
もし、しばらく経っても反応がない場合は、「届いているかどうかの確認」程度のやわらかい表現でフォローすると、押しつけがましくならずにすみます。
たとえば、
- 「先ほど再送させていただいたメールですが、無事届いておりますでしょうか」
- 「お忙しいところ恐れ入りますが、念のためご確認いただけますと幸いです」
といったように、配慮のあるトーンを意識すると好印象です。
再送後のひと声や軽いフォローは、相手との信頼関係を築く上でとても大きな意味を持ちます。
細やかな気遣いを欠かさないことが、ビジネスにおいて信頼を積み重ねていく土台になります。
まとめ
「メールが届いていない」と言われたときは、まず原因を確認し、そのうえで丁寧なお詫びとともに再送することが大切です。
状況に応じた表現を使い分けることで、信頼を損なわずスムーズにやり取りを進められます。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 再送前の確認 | アドレス・添付・送信環境を必ずチェック |
| お詫び表現 | 控えめかつ柔らかい言葉で伝える |
| 例文活用 | 相手との関係性に合わせた文面を選ぶ |
| フォロー | 再送後は届いたかを軽く確認する |
再送メールは単なる事務作業ではなく、信頼を保つための大切なやり取りです。
小さな気配りを積み重ねることで、相手に誠意が伝わります。

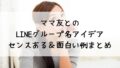
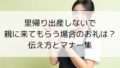
コメント