ビジネスメールでの「CC入れ忘れ」、意外と多くの人が経験しているのではないでしょうか。
ちょっとしたミスのつもりが、相手との関係や社内の信頼に影響することも。
この記事では、
- CC入れ忘れのお詫びメールの書き方
- 状況別の例文(社内・社外・再送時など)
- ミスを防ぐ工夫やチェックリスト
などをわかりやすく解説します。もうCCのミスで慌てないために、ぜひ最後までご覧ください。
CC入れ忘れのお詫びメールのポイント

ビジネスメールにおけるCCの役割を確認
ビジネスメールでは、CC(カーボンコピー)を活用することが、スムーズな情報共有において非常に重要な役割を果たします。
たとえば、プロジェクトに関係する部署のメンバーや、確認・承認が必要な上司などは、必ずCCに入れておくことで、後のトラブルや認識のずれを減らすことができます。
以下のように、CCを入れるべき代表的な相手をまとめておくと、日常の判断にも役立ちます。
| CCを入れるべきケース | 具体的な相手 | 理由 |
|---|---|---|
| 上司の確認が必要なとき | 部署の上司、マネージャー | 承認や経緯の把握が求められるため |
| チーム全体への連絡 | 同じプロジェクトのメンバー | 情報を均等に共有するため |
| 関連部門との連携がある場合 | 他部署の担当者 | 認識のズレや重複作業を防ぐため |
| 外部パートナーとの調整時 | 社内関係者 | 社内の進捗や対応履歴を残すため |
とくに複数人で連携して進める仕事や、やりとりの履歴を残しておきたい場合には、CCの役割がとても大きくなります。
CCを適切に使えば、後から「聞いていない」「知らなかった」といった行き違いを防ぐことができるため、業務全体の効率も上がります。
逆に、CCを忘れることで、知らず知らずのうちに相手に不快な思いをさせてしまうこともあるため、日常的に気を配りたいポイントです。
CC入れ忘れで起こりやすいトラブル
CCの記載を忘れてしまうと、以下のような困りごとが起きやすくなります。
- 上司や関係部署が情報を受け取っておらず、確認漏れが生じる
- 結果として同じ話をもう一度共有することになり、手間がかかる
- 「共有されなかった」という印象を与え、人間関係に影響を及ぼすことも
一見ささいなミスに思えるかもしれませんが、ビジネスの場では相手に与える印象がとても大切。
「この人は配慮があるな」と思ってもらえるか、「なんとなく信頼しにくいな」と感じさせてしまうかは、こうしたメール対応ひとつで大きく変わってきます。
お詫びメールで信頼を回復できるポイント
CCを入れ忘れた際には、素早く、かつ丁寧なお詫びメールを送ることで信頼を取り戻すことができます。
大切なのは、ただ謝るだけでなく、自分のミスを認めたうえで、今後に向けた前向きな姿勢を見せることです。
- なぜミスが起きたのかを簡潔に伝える
- 関係者への影響に配慮した言葉を添える
- 今後の対策や気をつける点を一言そえる
こうしたポイントを押さえることで、誠意のこもった対応となり、相手にも真摯な姿勢が伝わります。
また、気づいてすぐに対応することで、誠実さと責任感を印象づけることができ、結果として良い信頼関係の構築にもつながります。
CC入れ忘れのお詫びメールの基本的な書き方

件名の付け方と注意点
たとえば、
- 「資料共有の件」
- 「◯◯についてのご連絡」
といった表現であれば、読み手がすぐに要件を把握しやすくなります。
「お詫び」や「謝罪」などの強い言葉を件名に入れると、かえって重たく見えてしまうこともあるため、やわらかいトーンでまとめるのがおすすめです。
「再送のご連絡」「念のためのご確認」などの言い回しは、相手にプレッシャーを与えずに配慮を伝えられます。
また、件名が長すぎるとスマホなどで見切れてしまうこともあるので、30文字程度に収めるとより親切です。
緊急度や目的に応じて、「重要」や「再送」などのキーワードを頭に付け加えることで、開封率の向上にもつながります。
本文に盛り込むべき内容
お詫びメールの本文では、以下のポイントをおさえて構成することで、丁寧かつ落ち着いた印象を与えることができます。
- CCを入れ忘れたことに気づいたタイミングや理由
- すぐに対応し、再送または転送を行った旨
- ご迷惑をおかけしたことへの配慮と、今後の再発防止の工夫
この3点を過不足なく盛り込むと、読み手にも状況がわかりやすく伝わります。
たとえば、「本日午前中に送信したメールでCCに入れるべき方を失念しておりました」といった書き出しであれば、冷静な印象を保ちながら丁寧な説明が可能です。
あくまで事実を簡潔に伝え、言い訳がましくならないよう注意しましょう。
過度にへりくだるよりも、「このようなことがないよう、以後気をつけます」といった前向きな言葉を添えることで、誠実さが伝わります。
宛名や署名で気をつけること
宛名については、状況や関係性に応じて使い分けると好印象です。
たとえば、1対1のやりとりでは「◯◯さん」、複数人に向けたメールでは「皆さま」や「関係各位」といった表現が適しています。
また、署名は本文の最後に簡潔に入れておくことで、ビジネスメールとしての体裁が整います。
- 会社名
- 部署名
- 氏名
- 連絡先
など、必要最低限の情報をわかりやすくまとめましょう。
とくに社外向けのメールでは、署名が丁寧に整っているだけで信頼感が高まります。
シンプルながらも丁寧さを感じさせるように意識して記載すると、全体の印象がぐっと良くなります。
【状況別】CC入れ忘れお詫びメールの例文

社内宛てお詫びメールの例文
件名:資料送付の件(再送)
本文:
お疲れさまです。
先ほど送信いたしました会議資料に関するメールにて、本来CCに含めるべき関係者の方々への追加が抜けておりました。
ご確認や共有の観点から、大変ご不便をおかけし、申し訳ございません。
本メールにて、対象の方を正しくCCに含めたうえで、改めて資料を添付のうえ再送させていただきます。
なお、資料の内容自体には変更はございませんが、念のため再確認いただけますと助かります。
今後このようなことがないよう、送信前の確認を徹底いたします。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
件名:スケジュール調整の件(再送)
本文:
お疲れさまです。
先ほどのスケジュール調整に関するメールにおいて、関係部署の担当者をCCに含めるのを失念しておりました。
ご不便をおかけし、申し訳ございません。
関係者の方々を含めた状態で、本メールにて改めてお送りいたします。
お忙しいところ恐れ入りますが、内容をご確認のうえ、ご返信をお願いいたします。
今後はこのようなことがないよう、十分注意してまいります。
よろしくお願いいたします。
件名:ご依頼事項の進捗報告(再送)
本文:
お疲れさまです。
先ほどの進捗報告のメールにて、共有対象となる上司のアドレスをCCに含めておりませんでした。
大変申し訳ありません。
あらためて正しい宛先にて再送いたしますので、以下の内容をご確認くださいませ。
ご不明な点などありましたら、お知らせいただけますと幸いです。
今後は、送信前の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
社外宛てお詫びメールの例文
件名:◯◯のご連絡(再送)
本文:
お世話になっております。
本日、◯◯に関するご案内をお送りしましたメールにおいて、本来CCにお入れすべき関係各位への共有が漏れておりました。
ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
改めて、必要な方々をCCに含めた上で、同内容を再送させていただきます。
情報共有を目的としたご連絡であり、内容に変更はございませんが、あらためてご確認をお願い申し上げます。
今後はこうした不備が生じないよう、十分に留意いたします。
何卒よろしくお願いいたします。
件名:商品仕様に関するご連絡(再送)
本文:
お世話になっております。
先ほどお送りした商品仕様に関するご案内メールにつきまして、CC欄に必要なご担当者を含めるのを失念しておりました。
大変申し訳ございません。
つきましては、関係者を含めた正しい宛先にて、あらためて同内容を再送させていただきます。
お手数ではございますが、今一度ご確認いただけますと幸いです。
今後は送信前の確認を徹底し、同様のことが起きぬよう努めてまいります。
引き続き、何卒よろしくお願いいたします。
件名:契約関連のご案内(再送)
本文:
いつもお世話になっております。
本日お送りした契約に関するご案内メールにて、社内での共有対象となる方へのCCが抜けておりました。
ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
情報共有を目的として、あらためて正しい宛先にて再送いたします。
内容に変更はございませんが、念のためご確認いただけますと幸いです。
今後は再発防止に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
再送・転送時に使える例文と注意点
たとえば、「◯◯のご連絡(再送)」のようにしておくと、相手が過去のメールとの違いにすぐ気づけるため、見落としを防ぐ効果もあります。
本文の冒頭では、「先ほどと同内容になりますが、共有漏れがあったため再送いたします」などのひと言を添えると丁寧です。
また、内容を途中から省略せず、冒頭からすべて再掲して送るようにすると、受け手側の混乱を防ぐことができます。
相手に余計な手間をかけさせないよう、細やかな気配りを意識することが大切です。
件名:会議議事録の共有(再送)
本文:
お世話になっております。
先ほどお送りした会議議事録のメールにて、共有すべきご担当者の方をCCに入れ忘れておりました。
失礼いたしました。
あらためて、正しい宛先にて同じ内容を再送させていただきます。
内容自体は変更ございませんが、ご確認いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
件名:お見積もりのご案内(再送)
本文:
お世話になっております。
先ほどお送りしたお見積もりのメールについて、社内共有用の担当者がCCに含まれておりませんでした。
お手数をおかけして恐縮ですが、下記にて再送いたします。
今後は送信前の確認をより徹底してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
CC入れ忘れを防ぐための工夫

チェックリストを活用した確認方法
メールを送信する前に、ちょっとしたチェックリストを活用することで、うっかりミスを防ぐことができます。
以下のような項目を毎回意識するだけでも、精度の高いメール対応につながります。
- 宛先、CC、BCCの設定に誤りはないか確認した?
- 件名は内容と合っており、わかりやすくなっている?
- 本文の内容に漏れや重複、誤字脱字はない?
- 添付ファイルは正しいものがついているか?ファイル名は適切か?
- 不要な情報や他の案件が混ざっていないか?
- 開封後の相手がスムーズに内容を理解できる構成になっているか?
こうした項目を目視で1つずつ確認することを日常化することで、「ついうっかり」の防止になります。
部署内で共有できる簡易なチェックシートを作って、パソコンのモニター近くに貼っておくのも効果的です。
チームでの運用ルールづくり
個人の意識だけに頼るのではなく、チーム全体で取り組む体制づくりも欠かせません。
たとえば以下のようなルールを取り入れてみましょう。
- 重要なメールは送信前にペアで確認する(ダブルチェック)
- よく使う宛先やCCリストをテンプレートとして整備しておく
- 定型文や定型フローはマニュアル化して共有する
- チャットツールなどで「メール送りました」と一言共有する運用をルール化する
- メール文の一部に送信目的や背景を明記しておくようにする
こうした工夫を通じて、ミスが起きにくい仕組みづくりが可能になります。
今後の再発防止に役立つ習慣
日々の業務の中で次のような習慣を取り入れることで、再発を防ぎやすくなります。
- メール送信前に深呼吸し、読み返す「ひと呼吸チェック」
- ミスに気づいた時はメモや記録を残し、同じパターンを繰り返さないように意識する
- 月に一度、チーム内でメール対応に関するミニ勉強会や情報共有の時間を設ける
- メールを受け取った側の立場になって見直す視点をもつ
また、自分のミスを共有する文化があると、職場全体が前向きな雰囲気になります。
失敗を恐れすぎず、次に活かす姿勢を持ち続けることが、結果として丁寧で信頼されるメール対応につながっていきます。
まとめ|丁寧な対応と予防が信頼につながる
CCの入れ忘れは、小さな見落としから生まれることが多いですが、その後の対応しだいで印象は大きく変わります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| お詫びメールの基本 | 素早く・丁寧に・配慮を込めて。件名や本文の工夫が大切です。 |
| 状況別の例文 | 社内・社外・転送時など、シーンに応じた文例を活用するとスムーズです。 |
| 再発防止策 | チェックリストの運用やチームでのルールづくりでミスを減らせます。 |
丁寧なメール対応は、相手に誠意が伝わり、信頼関係を築く大きなきっかけにもなります。

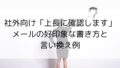
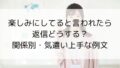
コメント