里帰り出産をしない、または親に来てもらわない選択をする家庭が増えています。
理由は人それぞれですが、そこには「夫婦で協力して育児を始めたい」「親に頼ることがかえって負担になる」といった背景があります。
この記事では
- 里帰り出産をしない理由やメリット
- 親に来てもらわない選択に込められた思い
- 夫婦で準備すべきポイントやサービス活用法
をわかりやすく解説します。
最後まで読むことで、自分たちに合った出産・育児スタイルを考えるヒントが見つかりますよ。
里帰り出産しない&親に来てもらわない家庭が増えている理由

そもそも「里帰り出産」とは?
出産の時期に実家へ帰り、親の手を借りながら出産や育児をスタートさせるスタイルが「里帰り出産」です。
これは長年、日本の家族社会においてスタンダードとされてきた育児のかたちであり、特に初めての出産に臨む方にとっては心強い選択肢のひとつとされてきました。
出産前後の体力的・精神的な負担を軽くし、家事や育児の役割を親に支えてもらえるという点でも、多くの家庭に受け入れられてきた背景があります。
以下のように、従来の「里帰り出産」にはいくつかの特徴があります。
| 里帰り出産の特徴 | 内容 |
|---|---|
| 支援体制 | 実家の母親などが家事・育児をサポート |
| 生活環境の変化が少ない | 実家という安心感のある場所で過ごせる |
| 育児の相談がしやすい | 育児経験のある親がそばにいてすぐ聞ける |
| 心身の回復がしやすい | 家事を任せられることで産褥期にしっかり休める |
しかし近年では、この「当たり前」とされてきたスタイルを選ばず、自分たちの生活基盤である自宅で出産後の育児を始めるご家庭も増加傾向にあります。
その背景には、
- 現代的な人間関係や家族のかたちの多様化
- 実家との物理的・心理的距離
- 夫婦で協力して子育てしたいという意識の変化
など、さまざまな要因が影響しています。
必ずしも「親に頼ること=ベストな選択肢」とは限らないという価値観が浸透しつつある今、里帰り出産をしないという選択肢が自然なものとして受け止められはじめています。
増えている背景と現代の育児スタイル
育児スタイルはこの数年で大きく変化してきました。
かつては「子供を産んだら実家に帰るのが当たり前」とされていたものが、今は
- 「他人に頼らず、一家で育児を始めたい」という思い
- 「親の負担を減らしたい」といった考え方
も出てきています。
それに加えて、仕事の部署や経済的な理由で夫婦で移動することが難しかったり、実家の親との関係の端々しさから、帰ることそのものがストレスになる場合もあります。
これらの要素が重なって、実家に頼らずに自家で育児を始める選択が、常識の一つとして拡がりつつあるのです。
なぜ親に来てもらわない選択をするのか【気持ちの整理】

精神的な負担や気疲れを避けたい気持ち
親のご好意でのアドバイスや、ちょっとした口出しが、一人で頑張ろうとしている母親にとっては、大きなプレッシャーになることもあります。
とくに初産の場合は、こんな気持ちが強くなりがちです。
- 自分の考えでやってみたい
- 何が正解かを探りながら経験してみたい
- 最初は失敗も自分のものとして受け止めたい
こんな前向きな意思に、たとえば本人は簡単な助言のつもりでも、
- 一言「それじゃ駄目よ」と声をかけられる
- 気づかないうちに何か代わりにされる
このようなことが自信をぐらつかせる要因になりがちです。
ただでさえ出産前後は体も心も不安定な時期。
そこに、
- 作戦の不一致
- 思いのすれ違い
- 誰にも話しづらい状況
などが重なると、ただただ不安で疲労だけが溜まってしまいます。
このような背景から、親に頼ることを遠慮し、自分たちのやり方で出産や育児を始めようと考える人が増えているのです。
夫婦で乗り越えたいという思い
「ふたりで新しい家族の形をつくっていきたい」という前向きな思いも、里帰りを選ばない選択を後押しします。
実際には、夫婦だけで協力しながら出産を迎え、そこからの育児を一緒に始めることで、既存の関係が更に深まりを増すことも多くみられます。
特に初めての子育ては不安や戻ってよくわからないことも多いため、夫が一緒になって応じるだけでも、太い支えとなります。
その結果、
- 役割分担
- 家事
- 育児
に対する理解は、意識して何かを教えるのではなく、経験を通じて自然に潰漏と踏み落とされていくようになります。
お互いの努力や応援がめざましく覚えられる分、その後の家庭生活も基盤から相互理解のひとこまとなり、一幸に子育てをしていくための不可欠な基盤を作り上げるチャンスにもなるのです。
里帰り出産をしないメリットと不安点

自宅での出産準備・生活がしやすい面
住み慣れた自宅で、めまぐるしい生活リズムを突然変えることなく、ある程度自分のペースで過ごせるのは、落ち着いた気持ちで出産後を迎えるための大きな利点です。
以下のように、自宅での生活には具体的なメリットが多くあります。
| 自宅で過ごすメリット | 内容 |
|---|---|
| ペースを崩さず生活できる | 生活リズムを維持しながら、自分のペースで過ごせる |
| 通院や準備がしやすい | 地元の病院を利用できるため、移動の手間や引っ越しの必要がない |
| 非常時も自宅で対応可能 | 育児用品や設備が整っていれば、急なトラブルにも自宅で落ち着いて対応できる |
| 生活環境が整っている | 必要な家具や日用品がすでに揃っており、探し物などのストレスが少ない |
| 環境の変化が少なく心身にやさしい | 部屋替えや生活スタイルの変化が少ないため、体力回復やメンタル面のケアがしやすい |
| パートナーのサポートを受けやすい | 夫がそばにいる時間が長ければ、感情面でも支えになり、負担を分け合える |
このように、自宅での出産後の生活は心と体の両面にやさしく、安心して過ごせる土台となります。
特に夫が近くにいてくれる場合は、気持ちを共有できる場面も増え、一人で抱え込まずに済むのが大きなポイントです。
乗り越えるべき課題や孤独感とは?
特に夜間の授乳や赤ちゃんのお世話が続くと、気力が追いつかない場面も出てきます。
そんな時に、話を聞いてくれる相手が近くにいないと、これまでないほどの孤独を感じる場合もあります。
ある意味では、里帰りをしないという選択は「これから一家のあり方をどう組み立てていくか」を実際に体験する準備期間とも言えます。
だからこそ、無理をせず、ほっと心を緩めて、できるだけサポートも上手に取り入れながら、自分自身を大切にして過ごしていきたいです。
出産前から必要な準備と心構え

夫の協力体制がカギになる理由
親に頼らないスタイルでは、夫のサポートがとても重要になります。
出産や育児は、母親だけの負担ではなく、夫婦で協力して進めるべきもの。夫がどれだけ積極的に関わるかによって、産後の生活のしやすさが大きく変わります。
育児や家事は「手伝う」のではなく、「一緒に担う」ものという意識を持ってもらうことがスタートラインです。
具体的には、
- 産後のスケジュールや赤ちゃんのリズムを夫婦で共有しておく
- 沐浴・ミルク・おむつ替え・抱っこ・寝かしつけなど、基本的な育児スキルを一通り習得してもらう
- 夜中の対応は交代制にする、あるいは早朝のミルクやオムツ替えを担当してもらう
- 掃除や洗濯・食事の準備など、生活全体を支える役割についても話し合っておく
このような協力体制を出産前から整えておくことで、「ママだけが頑張る」という状態を避けやすくなります。
加えて、夫が主体的に動く姿勢を見せてくれると、産後の心の支えにもなり、産後うつや孤独感を感じにくくなるというメリットも。
「お互いを思いやる」ことを前提とした関係づくりが、夫婦だけで乗り切る出産をより前向きなものにしてくれます。
産褥期を見据えた環境づくり
産後は身体をしっかり休めることが大切です。
無理をして動きすぎてしまうと、回復が遅れたり体調を崩す原因にもなりかねません。
たとえば、冷凍食品やレトルトをストックしておいたり、生協やネットスーパーの宅配を活用したりするのも有効です。
掃除はお掃除ロボットや家事代行を検討してもいいでしょう。日々の小さなストレスを減らすことが、体調を整えることにつながります。
また、寝室と赤ちゃんスペースを同じにすることで、夜中の授乳やおむつ替えの動線が短くなり、身体への負担も軽減されます。
なるべく動かずに済むよう、ベッドの近くにオムツや授乳用品をまとめておくと安心です。
育児グッズ・生活導線の工夫
産後すぐに必要になるアイテムは、あらかじめ準備しておくとスムーズです。
特に使用頻度が高いアイテムは、手の届く範囲にまとめておくと、無駄な動きを減らすことができます。
- 授乳グッズ:授乳クッション、授乳ケープ、哺乳びんなど
- 温度管理用品:体温計、温管、電子ケトル
- 着替え類:ロンパースやパジャマ、洗替用の服類
- 便利品:フィードクッションコーナー、ハンドソープ
2階建てのおうちであれば、1階と2階に最低限のお世話グッズを配置しておくのがポイントです。毎回階段を上り下りする手間や負担を減らせます。
また、赤ちゃんスペースには、ベビーベッドのほかにも、下詰めマットやゴミ箱、使いがっての良い光量管理カーテンなど、必要なものをセットで用意しておくと便利です。
これらをそれぞれ分散させずに「育児コーナー」のようにまとめて配置することで、採烱やお世話の動線を短くし、体力の消耗を抽象的に減らすことができます。
生活導線を意識したレイアウトにすることで、余計な動きを減らせるだけでなく、赤ちゃんとの生活にリズムが生まれ、自然と育児がしやすい環境になります。
周囲の支援とサービスを上手に使う

ファミサポや訪問助産師の活用方法
自治体が提供しているファミリー・サポート・センター(通称ファミサポ)は、出産後の子育てにおいて頼れる存在です。
ファミサポの特徴として、以下のような支援内容があります:
- 短時間の託児サポート:必要なときに短時間だけ子どもを預かってもらえる
- 保育園の送迎支援:保護者が難しい場合に送迎を代行してもらえる
- 育児の補助や相談相手:身近な育児の相談にも対応してくれる
これらのサービスによって、
- 子どもと少し離れる時間を持ってリフレッシュしたり、
- 上の子のお世話が必要なときにも柔軟に対応できたりと、 育児を無理なく続けるための大きな支えになります。
利用にあたっては簡単な面談や事前登録が必要ですが、料金も比較的手頃で、定期的な依頼もしやすい点が魅力です。
また、地域によっては、産後ケア事業の一環として助産師さんが自宅を訪問してくれる支援も整備されています。
たとえば、
- 授乳のコツや姿勢のアドバイス
- 沐浴のやり方の実践サポート
- 産後の体調や気持ちの変化への助言 など、専門的な知識をもった助産師さんが、マンツーマンでサポートしてくれます。
「誰かに話を聞いてもらうだけで気が楽になる」と感じることも多いため、ひとりで抱え込まず、こうした地域サービスを積極的に取り入れていくことが大切です。
家事育児の外注や行政支援も検討を
掃除や洗濯を外注することに対して「贅沢かな」と思う方もいるかもしれませんが、出産直後は特別な時期。
心と体の回復のためにも、無理せず頼れるものは取り入れていくことが必要です。
また、自治体が行っている育児支援制度や産後ヘルパーの派遣なども、対象期間や利用条件を事前に確認しておくと安心です。
中には出産後すぐの申請が必要なケースもあるため、妊娠中から情報を集めておくのがおすすめです。
「ひとりで全部やらなきゃ」と気を張らず、できること・できないことを冷静に整理して、信頼できる人やサービスの手を借りることも、立派な育児の一部といえます。
まとめ
最後に、里帰り出産をしない&親に来てもらわない選択のポイントを表に整理しました。
| 選択の背景 | メリット | 課題 |
|---|---|---|
| 実家との距離、夫婦でやりたい気持ち | 自宅で落ち着いて過ごせる/生活リズムを崩さずに済む | サポートが少なく孤独感を感じやすい |
| 親への気遣いや口出しの負担 | 自分の育児スタイルを築ける/夫婦の絆が深まる | 産後の疲れや不安を抱え込みやすい |
夫婦で協力しながら育児を始めることで、新しい家族の形を築く大切なチャンスにもなります。無理をせずサービスや支援を取り入れ、自分たちらしいスタイルを見つけていきましょう。

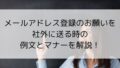
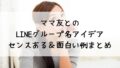
コメント