通知表の「おうちの人からひとこと」欄、何を書けばいいのか毎回悩みますよね。
我が子の頑張りをきちんと伝えたいけど、いざ言葉にしようとすると難しい……。
そんなモヤモヤを感じたことがある方に向けて、この記事では通知表にふさわしいコメントの例文を学年別・目的別にわかりやすくご紹介します。
通知表にふさわしいおうちの人からのひとこととは

おうちの人からのコメントの重要性
通知表に添えられる保護者のコメントは、子どもにとって大きな励みになります。
ただ成績や評価を見るだけでなく、おうちの人の言葉から「自分の頑張りが認められている」と感じられることで、子どもは次のステップへの意欲を高めることができます。
また、先生に対しても、家庭での子どもの様子や保護者の思いを伝える貴重な手段です。
例えば、家庭での取り組みや日々の努力を具体的に書くことで、学校側もより深く子どもを理解する手助けになります。
単なる形式的な一文ではなく、子どもの努力や成長に気づき、認めるメッセージが求められます。
それによって、子ども自身が自信を持ち、保護者と教師の信頼関係も築かれていきます。
通知表コメントの目的と役割
通知表コメントの目的は、子どもの頑張りを言葉にして認めること、今後への期待や応援の気持ちを伝えることにあります。
学習面だけでなく、生活態度や友人関係、日常の中での成長にもしっかり目を向け、それを文章に表すことで、子どものモチベーションアップにつながります。
また、家庭と学校の連携を深めるためのコミュニケーション手段としても重要です。
コメントを通じて、担任の先生が保護者の考えや期待を把握できるため、子どもへの支援の方向性もより明確になります。
どんなコメントが効果的か
効果的なコメントは、「具体的な成果」や「努力した過程」に触れたものです。
- 「毎朝自分から音読をしている姿に感心しました」
- 「忘れ物が減ってきて、自分で準備できるようになってきました」
など、家庭での小さな変化を取り上げると、先生にも伝わりやすく、子どもにも励みになります。
また、過度に結果だけを褒めるのではなく、努力の過程や挑戦する姿勢を評価する言葉も大切です。
子どもが「がんばったことがちゃんと見えている」と感じられるように、日常の中での取り組みを丁寧に拾い上げるコメントを意識しましょう。
小学校・中学校別の通知表「おうちの人からひとこと」例文
1年生のための例文集
4年生や6年生向けのコメント例
中学生用コメントのポイント:例文
学期ごとの通知表コメントの書き方

1学期・2学期・3学期の違い
【1学期】:新しい学年への適応や目標への意気込みに注目。新しいクラスメートとの関係づくりや、担任の先生との関わりの中でどのように行動できたかを見守ることが大切です。また、学校生活への意欲やルール理解の様子にも触れると良いでしょう。
【2学期】:学習内容の深まりや継続的な努力の評価を中心に。1学期の経験を踏まえての取り組みの変化や、学習に対する意識の成長を記述します。運動会や音楽発表会などの学校行事にも積極的に参加する姿勢を認めると、よりバランスのとれたコメントになります。
【3学期】:1年間のまとめと、次年度への期待を込めた内容が望ましいです。これまでの成果や成長を具体的に振り返り、「〇〇ができるようになって自信がついたね」など、努力の結果を認める言葉を使いましょう。そして「来年度も引き続き△△に取り組んでほしい」など、次のステップへの期待も自然に盛り込みます。
成長を促すための書き方
努力を認めるとともに、
- 「〇〇ができるようになったね」
- 「次は△△にも挑戦してみよう」
など、前向きなステップアップを促すコメントが理想的です。
また、達成できなかったことも「惜しかったね」「あと少しでできそうだったよ」と前向きに表現し、次に向けてのやる気を引き出すことが大切です。
子ども一人ひとりの個性に寄り添い、その子らしさを認める視点を忘れずに書くと、温かみのあるコメントになります。
経験を活かしたコメントの工夫
子どもが学んだ経験を振り返り、それを今後どう活かしていくかに触れると、成長の連続性が感じられる文章になります。
たとえば、
- 「グループでの発表を通じて、人前で話すことに自信を持てたようです」
- 「夏休みの自由研究では、自分の好きなことにじっくり取り組む姿勢が見られました」
など、過去の経験が現在につながっていることを示すと良いでしょう。
また、学校外での体験や、家庭でのちょっとした挑戦も含めることで、子どもの成長を多角的に評価できます。
こうした工夫により、通知表のコメントは単なる評価ではなく、次の一歩を応援するメッセージとしての価値を持ちます。
子どもたちへの具体的なメッセージ・例文
成績向上を応援する言葉
苦手科目への励ましの一言
生活面での成長を称えるメッセージ
通知表コメントで気をつけるべきNG例
ネガティブな言葉を避ける
- 「どうせできない」
- 「全然ダメ」
など、否定的な表現は避けましょう。
こうした言葉は子どもの自己肯定感を損なう原因となり、今後のやる気にも悪影響を及ぼしかねません。
代わりに、「あと少しでできそうだったね」「ここまでよく頑張ったね」といった前向きな言葉に言い換えると、子どもの意欲を育てることができます。
注意点を伝える場合も、できるだけポジティブな言い回しで改善の方向性を示すことが大切です。
具体性を欠いたコメントの危険
「頑張っていました」だけでは伝わりづらいです。
どのような場面で、どんな工夫をして努力したのかを具体的に書くことで、説得力が生まれます。
たとえば、
- 「毎朝の音読を欠かさず取り組んでいました」
- 「苦手な漢字練習も、自分で時間を決めて取り組む姿勢が見られました」
など、行動の内容を具体化することで、先生にも伝わりやすくなります。
具体性はコメントの信頼性と温かみを高める鍵です。
家庭内での適切な表現方法
例えば「集中力が続かないように感じていますが、興味を持てる教科では意欲的に取り組んでいます」といった、課題と良い点を両方取り入れた表現にすることで、先生にも配慮を伝えながら、子どもの意欲を傷つけない内容にすることができます。
子どもの成長を支えるための前向きなコミュニケーションを意識しましょう。
コメントのまとめ方と一言の工夫
感謝の気持ちを伝える言葉・例文
目標設定のためのメッセージ
学校生活への期待を込めた一言
保護者として知っておくべき注意点

担任の先生との連携の重要性
通知表コメントは、先生との意思疎通にも役立ちます。
子どもの学校での様子と家庭での様子には違いがあることも多く、保護者が自宅で感じた子どもの変化や頑張りを伝えることは、教師にとっても非常に貴重な情報源となります。
先生と家庭が連携を深めることで、子どもを取り巻く環境がより良くなり、成長を後押しする土台が築かれていきます。
子どもの学校生活への関わり
通知表をきっかけに、家庭でも学校生活について話し合う時間を持つと良いでしょう。
子ども自身の言葉で学びを振り返る機会にもなりますし、学校での出来事や感じたことを親に話すことで、自分の行動を客観的に見つめ直すきっかけにもなります。
また、通知表のコメントについて親子で一緒に考えることで、子どもが家庭で大切にされていると実感し、学校生活に対してもより意欲的に取り組めるようになることがあります。
話し合いの中では、否定や批判ではなく、受け止めて寄り添う姿勢を心がけると、より良い親子関係の構築にもつながります。
【まとめ】
通知表に添える「おうちの人からひとこと」は、子どもを励まし、先生との信頼関係を深める大切なコミュニケーション手段です。
以下に効果的なコメントのポイントをまとめました。
| ポイント | 内容の例 |
|---|---|
| 努力の具体化 | 「毎朝の音読を続けている姿に感心しています」 |
| 前向きな言葉選び | 「あと少しでできそうでした」「挑戦する姿が素晴らしい」 |
| 成長への期待 | 「来年度も新しいことに挑戦していってほしいです」 |
温かみのある言葉で、子どもの自信とやる気を引き出しましょう。

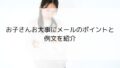
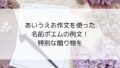
コメント