幼児向け絵本のストーリー例を探している方へ!
どんなテーマや展開にすれば、子どもの心をつかめるのか迷いますよね??
そこで、この記事では以下の内容をご紹介します。
- 今すぐ使えるストーリー例5選
- アイデアに困らないネタの作り方
- 絵本制作の流れとテクニック
「楽しくてためになる絵本」を作るヒントがきっと見つかりますよ!
4ステップで完成!幼児向け絵本の作り方

子供は本当に絵本が好き。自分で絵本を制作することができれば、それは素晴らしい経験になります。
家族での読み聞かせが日常の一部となっている家庭も多いでしょう。
我が家でも、読み聞かせは夜のルーティンです。
短いストーリーの絵本を自分たちで作る時、まずはどんなテーマで進めるか決めましょう。
そのテーマを基に物語を膨らませていきます。
絵本作りの基本手順を把握し、作成の流れをイメージしてみましょう。
以下にその手順を説明します。
●基本的な絵本の作り方
・必要な材料を準備する
・下書きを描く
・ペンで書き込み、仕上げる
これらのステップを踏むことで、手軽に絵本を作成できます。
まずは、幼児向けの絵本作りの参考になる、ストーリーの例をご紹介します。
すぐ使える!幼児向け絵本ストーリーの具体例5選

幼児向けの絵本ストーリーは、身近なもの・わかりやすい展開・優しい結末がポイントです。
ここでは、すぐに使える短いストーリー例を5つご紹介します。テーマや構造も明記しているので、カスタマイズも簡単ですよ。
①くまさんとケーキのひみつ
テーマ:分け合う心/動物×食べ物
起:
ある日、森を散歩していたくまさんは、大きくてふわふわのケーキを見つけました。甘い香りが広がっていて、見るからにおいしそうです。「わあっ、これはぼくのだ!」と目を輝かせます。
承:
「ひとりで全部食べよう!」とくまさんは大喜びでケーキを運び始めます。ところが、その途中でうさぎやたぬき、ことりたちと出会います。みんなケーキに気づいて「いいなあ」「おいしそうだね」と話しかけてきました。
転:
くまさんはちょっぴり困った顔に。「ぼくが見つけたケーキだけど…みんなも食べたいのかな」と心の中でぐるぐる考えます。でも、友だちがニコニコと楽しそうにしているのを見て、「いっしょに食べたらもっと楽しいかも」と思いはじめます。
結:
くまさんはケーキを分けて、「みんなで食べよう!」と声をかけました。動物たちは大喜びで、「ありがとう、くまさん!」と集まってきます。みんなで分け合って食べたケーキは、今まで食べた中で一番おいしく感じました。
解説:
「共有」「友情」など、優しい気持ちを学べるストーリーです。登場キャラの心の動きや表情の描写を入れることで、感情移入しやすくなり、読んだあとに心があたたまる内容に仕上がります。
②バスがしゃべった!
テーマ:乗り物への親しみ/想像力を育む
起:ある朝、ぼくがいつものようにバス停でバスを待っていると、大きな声で「おはよう!」とバスが話しかけてきました。びっくりして思わず後ろをふりかえると、ほかの人は気づいていない様子。バスがしゃべったのは、どうやらぼくにだけみたいです。
承:少し緊張しながら「おはよう…」と返すと、「今日は一緒に楽しい冒険をしよう!」とバスが元気に言いました。バスの中では、窓の外の景色を見ながら、バスといろんな話をしました。「ぼくはどんなところを走るのが好き?」「今日はお客さん少ないね」など、まるで友だちのようです。
転:ところが突然、バスが「今日は道をまちがえちゃった!」と大慌て。地図を見るのが苦手なバスは、どこを走っているのかわからなくなってしまったのです。乗っていたほかのお客さんも「この道じゃないよね?」とざわざわし始めました。
結:ぼくはスマホで地図を開いて、近くの交差点を目印にしながらバスに道を教えてあげました。「まっすぐ行って、右にまがると戻れるよ!」と声をかけると、バスは「ありがとう!」と大きな声で笑いながら元の道に戻りました。そのあともぼくとバスは仲良くおしゃべりしながら目的地まで向かいました。
解説:
乗り物好きの子どもに大人気の題材。「もし◯◯が話せたら?」という設定で想像の幅が広がり、会話を通じて優しさや思いやりも自然と学べるストーリーです。
③はるちゃんのごあいさつチャレンジ
テーマ:あいさつ/習慣づけ
起:はるちゃんは、ちょっぴり人見知りで、知らない人に話しかけられると恥ずかしくなってしまいます。幼稚園に入る前に、元気にあいさつができるようになりたいと思っていましたが、なかなか勇気が出ません。
承:ある日、ママが「おはようチャレンジ」というゲームを考えてくれました。朝、近所の人や通りすがりのおばあちゃんに「おはよう」と言えたら、シールがもらえるのです。はるちゃんはちょっと照れながらも、ママと手をつないでチャレンジを始めます。
転:はじめのころは、声が小さすぎて相手に聞こえなかったり、もじもじして言えなかったり。でも、ママがやさしく見守ってくれて、成功した日は一緒にたくさんほめてくれました。少しずつ、はるちゃんの表情が明るくなり、声も大きくなっていきました。
結:ある日、公園で出会った近所のおじいちゃんに、自分から「こんにちは!」と言えたはるちゃん。おじいちゃんがにっこり笑って「こんにちは、はるちゃん」と返してくれて、胸がぽかぽかに。はるちゃんはその日、一番キラキラのシールを貼ってもらいました。
解説:
入園前や小さい子どもに向けて、「あいさつは楽しい」「できたことが自信につながる」という前向きなメッセージを込められるお話です。親子で取り組める習慣づけのヒントにもなります。
④かさをなくしたぞうくん
テーマ:忘れ物・自己解決/日常の出来事×成長
起:ぞうくんは、雨がしとしと降る朝に、大好きな水玉のかさを持って幼稚園へ行きました。玄関で先生に「おはようございます!」と元気にあいさつし、靴をぬいで傘立てにかさをさしました。
承:楽しく一日を過ごして、帰りの時間になりました。ぞうくんはかさを取りに行きましたが、そこにはもう水玉のかさが見当たりません。何度も見直して、「あれ?ぼくのかさがない!」と慌ててしまいます。
転:ぞうくんは泣きそうになりますが、「じぶんでさがす!」と深呼吸して決めました。教室のすみ、トイレの前、遊戯室のはしっこなど、あちこちをていねいに探して歩きます。途中、友だちのきりんくんが「いっしょに探そうか?」と声をかけてくれました。
結:ふたりで協力して探していたところ、玄関のかごの中に、誰かが移動させたらしい水玉のかさを見つけました。ぞうくんは思わず「見つけた!これ、ぼくの!」と声を上げてにっこり笑顔に。先生も「自分で見つけられてえらいね」とほめてくれて、ぞうくんの心はぽかぽかになりました。
解説:
「忘れ物」「困ったときの行動」など、実生活に結びつくテーマで保育・子育てにも使いやすい一編です。自己解決力や友だちとの助け合い、成功体験の大切さもやさしく描かれています。
⑤おにぎりぴょんぴょんの旅
テーマ:食べ物×冒険/ユーモアを加えて
起:お弁当箱の中で眠っていたおにぎりの“ぴょんぴょん”が、ふと目を覚ましてジャンプ!「外の世界ってどんなところだろう?」とワクワクしながら、お弁当箱のフタのすき間からぴょん!と飛び出しました。
承:ぴょんぴょんは最初ににんじんさんと出会います。「こんにちは!どこへ行くの?」とにんじんさん。「ぼく、冒険に出るんだ!」と元気に答えるぴょんぴょん。次に出会ったのは、たまごやきくん。「いっしょに行ってもいい?」と仲間が増えて、わいわい道を進みます。花のにおい、風の音、小さな虫たち…すべてが新鮮で楽しい発見ばかりです。
転:ところが森に入ったとたん、大きなカラスが「おいしそうなおにぎり発見〜!」と空から急降下!ぴょんぴょんたちは大あわてで逃げ回ります。「たすけて〜!」と声を上げると、そこへ落ち葉の中から昆布くんが現れ、「こっちにかくれて!」とナイスフォロー!
結:カラスが去ったあと、みんなでホッとひと息。「もうそろそろ戻ろうか」と、ぴょんぴょんたちはお弁当箱に帰ることに。ちょうどそのとき、お昼の時間になっていて、子どもたちがフタを開けて「わあ、おいしそう!」とにっこり。旅を終えたぴょんぴょんたちは、みんなにおいしく食べてもらって、大満足の冒険になりました。
解説:
キャラが生き物のように動く、ユーモラスな展開。冒険・出会い・ピンチ・帰還という起承転結がしっかりとあり、お弁当や遠足の季節にもぴったりな題材です。
迷ったときに役立つ!絵本ネタのテンプレート集!

「絵本を作りたいけど、どんな話にすればいいか思いつかない…」
そんなときに便利なのが、「ストーリーの型」を知っておくことです。
型に沿って考えれば、自然と物語が広がり、アイデア出しの時間を短縮できます。
ここでは、初心者でも使いやすく、幼児向け絵本にぴったりなテンプレート5選を紹介します。
①キャラクター×困りごと×解決テンプレート
王道で汎用性抜群!日常系から冒険系まで使える型!
キャラクターの魅力と、成長のプロセスをしっかり描けるのが特長です。感情の起伏や友情、努力なども盛り込みやすく、読者に共感されやすい構成です。
- 主人公:だれ?どんな性格?(例:うさぎのピョン/ちょっと泣き虫)
- 困りごと:どんな問題が起きるか(例:だいすきなおもちゃが壊れた)
- 感情の反応:どう思った?どう感じた?(例:悲しくて泣いてしまう)
- 協力者:だれが助けてくれる?(例:くまくんがやさしく声をかけてくれる)
- 解決方法:どうやって解決したか(例:ふたりで部品を集めて修理)
- 成長や学び:主人公はどう変わった?(例:自分で直すことに挑戦できた)
- 活用例:「うさぎのピョンとこわれたラッパ」
②「もし◯◯だったら?」妄想ふくらむテンプレート
空想好きな子にぴったり。
発想の自由度が高く、日常のモノや風景にもしもの命を与えることで、豊かな想像力を刺激します。非現実的でも「こうだったら楽しいね」というワクワク感が大切です。
- 設定:もし◯◯が△△だったら?(例:もし冷蔵庫がしゃべったら?)
- 出発点:どうしてそうなった?(例:満月の夜に突然しゃべり出した)
- 展開:どんなふうにびっくりする?/どう関わる?(例:冷蔵庫と会話しながら朝ごはんを選ぶ)
- 変化:関係性や世界がどう変わる?(例:他の家電もしゃべるようになった)
- オチ:最後はどうなる?(例:朝になったらまた静かに戻った)
- 活用例:「おしゃべりれいぞうこのひみつ」
③季節イベント×ちょっとしたハプニングテンプレート
季節の行事+小さな事件を組み合わせることで、子どもが親しみやすく、共感しやすい内容になります。
準備のわくわく、思わぬトラブル、そして解決までの流れが自然に組み込めます。
- 行事:いつ?なにをする日?(例:ひなまつり)
- 準備の様子:どんな楽しみがある?(例:飾りつけや着物に着替える)
- ハプニング:ちょっとした問題(例:ひなあられが消えた!)
- 原因と気づき:なぜ起きた?(例:うっかり犬のポチが食べてしまった)
- 解決・教訓:どう乗り越える?何を学ぶ?(例:みんなで作って楽しくすごす大切さ)
- 活用例:「ひなあられはどこ?」
④数や色をテーマにしたリズム型テンプレート
くり返しや音のリズムがポイント。
視覚や聴覚にうったえる展開で、言葉のリズムとテンポが楽しい型です。乳幼児にも響く構成なので、読み聞かせにも最適です。
- モチーフ:数・色・形・音(例:いろんな色のくつした、にこにこ数字のなかま)
- くり返し展開:◯◯が△△する(例:あかいくつしたがぴょん!つぎはあおいくつしたがくるりん!)
- リズム:擬音語やリズムフレーズを入れる(例:ぴょんぴょん、くるりん、ごろごろ、ころん!)
- 構成例:順番に1〜5の数が出てくる/赤・青・黄・緑・ピンクの順に出てくる
- まとめ:最後に全部がそろう/違いを楽しむ/うたやダンスに発展(例:カラフルくつした行進! みんなでステップ♪)
- 活用例:「ぴょんぴょんくつした いろいろあるよ」「すうじのダンスパーティー」「いろいろドーナツ どれたべる?」
⑤感情×成長テンプレート
怒る・泣く・さびしい…子どもが共感しやすい感情を軸に。
感情の表現を肯定的に描きながら、そこからの変化や気づきを通して心の成長を描く型です。親子で読みながら感情の名前や伝え方を学ぶ導入にもぴったりです。
- 感情テーマ:どんな気持ち?(例:怒って泣いちゃった/さびしくて黙っちゃった)
- きっかけ:なぜそうなった?(例:おもちゃを取られた/遊ぶ約束を忘れられた)
- 気持ちの経過:どう感じ、どう反応した?(例:泣きたくなって走って行った)
- 支えや気づき:だれかの言葉や行動で変化(例:ママが「気持ちを言っていいんだよ」と教えてくれた)
- 成長:どう気持ちが変わった?(例:「ごめんね」と言えた/「いっしょに遊ぼう」と言えた)
- 活用例:「プンプンまると なかなおりの魔法」「なきむしドラゴンとほしのハンカチ」
【補足表】テンプレート比較表
| テンプレ名 | 主なテーマ | 難易度 | こんなときにおすすめ |
|---|---|---|---|
| キャラ×困りごと×解決 | 日常・冒険 | ★☆☆ | まずは定番から始めたいとき |
| もし◯◯だったら? | 空想・発見 | ★★☆ | 想像力をのびのび広げたいとき |
| 季節×ハプニング | 行事・共感 | ★★☆ | 季節感を取り入れたいとき |
| 数・色リズム型 | 知育・音遊び | ★☆☆ | 短めでくり返しが効く話にしたい |
| 感情 | 気持ち・共感 | ★★☆ | 子どもの気持ちに寄り添いたいとき |
子供向け絵本制作のネタ探しのポイント

子供向けの絵本を作る際のネタ探しは、少しのコツを押さえるだけでずっと楽になります。
絵本を作る初めのステップとして、最も頭を悩ませるのがテーマ選びです。
特に子供が理解しやすく、教育的な価値も含む内容が望ましいですね。
今回は、誰でも簡単に絵本のテーマを見つけるための4つのポイントを紹介します。
●アイデア探しの4つのポイント
・身近な出来事
・既存の絵本やアニメ
・自分が伝えたいメッセージ
これらのポイントを抑えれば、テーマは意外と身近に転がっていることに気づくはずです。
さあ、一緒に楽しい絵本のテーマを探しに行きましょう!
アイデア1【子供が興味を持つもの】
子供が好きなものをテーマにすると、子供に喜ばれること間違いなしです。
子供は自分の好きなものが登場する絵本を何度も何度も読み返します。
(本当に何度も…)
例えば、私の子供は乗りもの(特にバス)の絵本が大好きで、何度も繰り返し読んで楽しんでいます。
子供の興味を引くテーマで絵本を作れば、愛される作品になるでしょう。
そして、大人になった時に「あの頃はこれが好きだったんだよね」と振り返る素敵な記憶にもなります。
アイデア2【日常の出来事】
日常生活の中にも、絵本のアイデアはたくさん隠れています。
例えば、「公園で大雨に降られた話」や、「初節句のお祝いの話」や「兄弟とのけんかとその後の仲直り」などがあります。
よく考えてみれば、日常はアイデアに溢れています。
季節のイベントや日々の小さなエピソード、子供の予想外の行動など、すべてが素材になり得ます。
日常をテーマに絵本を作ることで、その時々の感情や思い出を未来に残すことができます。
この記事を読んだら、普段の生活を見直して、「これは絵本になるかも」と思える瞬間を探してみてください。
アイデア3【絵本やアニメから学ぶ】
他の絵本や子どもが観るアニメーション、さらには異なるアート作品から着想を得る方法もあります。
これらは既に人気のある作品ですので、それらをベースにオリジナルのストーリーを構築しやすくなります。
直接的な模倣は避けて、お気に入りのアニメの登場人物の未知のエピソードを創造するなど、新しい物語を生み出しましょう。
どのようにしてこのインスピレーションを物語に拡大できるかが鍵となります。
アイデア4【自分の伝えたいメッセージ】
伝えたいメッセージやテーマがある場合、それを物語の出発点としてください。
「おもちゃは大切に」や「ごはんを残さずに」といった具体的なテーマを物語に取り入れることで、親子の絆を深める作品が作れます。
自分自身の経験や感情を物語にすることで、より心に残る絵本が完成します。
テーマに合わせて、キャラクターや背景に動物や食べ物を取り入れると、ストーリーが豊かになり、書きやすくなります。
絵本は、短いストーリーでも手軽に作成できることが理解できたはずです。
思いもよらない場所に、次の素晴らしいアイデアが隠れているかもしれませんね!
幼児向け絵本のストーリーテリング基礎とテクニック

アイデアが決まったら、次にストーリーの展開を考えましょう。
物語を構築する方法は主に二つあります。
一つは古典的な「起承転結」に従って組み立てる方法、もう一つは物語の結末から逆算して考える方法です。
どちらの方法も物語作りに役立ちますので、自分に合った方を選んで試してみてください。
物語の基本構造「起承転結」
「起承転結」とは、物語や文章を明快に伝えるための構造です。
この方法に従うことで、内容が整理され、聞き手にとって理解しやすくなります。日本の多くの伝統物語や童話がこの形式で語られています。
「起承転結」の構造を使って物語を描くと、読者の興味を引きやすくなります。
●「起」— 物語の始まり
物語の始まり、すなわち「起」では、物語の発端となる出来事が設定されます。
例えば、「ある森の中に、魅力的なケーキが登場します。」
●「承」— 展開
物語が展開していく段階です。ここでストーリーが深まり、登場人物が活動を開始します。
例:「そのケーキを見つけたリスが、独り占めしようと企みます。」
●「転」— 高まり
物語のクライマックスに向けて、予期せぬ出来事や衝突が生じます。この部分で物語は最も盛り上がります。
例:「しかし、うさぎが現れて共有を提案し、その後に他の動物たちも参加して大きな騒動に。」
●「結」— 解決
「転」で発生した事件や問題の結末を描きます。これが物語の終わりで、教訓やメッセージが伝えられる部分です。
例:「最終的には、ケーキはみんなで分け合うべきだったという教訓に至ります。」
物語の分量の配分に関しては、全ての段階を均等に扱う必要はありません。
「起」は短めに設定し、興味を引くための「承」と「転」を長く取ることが多いです。
「結」は短くても内容が濃いものが理想的です。ただし、絵本の場合はこれらの比率に囚われ過ぎず、自然な流れを意識することが重要です。
以上の方法で物語を構築することで、聞き手にしっかりとした印象を残すことができるでしょう。
【テクニック】結末から物語を組み立てる
多くのアイデアが頭の中にあるのに、それを整理できずに困っていることはありませんか?
一般的には物語は「起承転結」の流れで作られることが多いですが、時にはこの枠組みに当てはめるのが難しいことも。
そんなときは、物語の結末から逆算してみるのがおすすめです。
結末を最初に設定することで、どのようにその点に至るかのプロットがスムーズにまとまります。
メッセージや教訓がはっきりしている場合、この方法が特に効果的です。
物語の終わりを考えてからでも、起承転結に沿って書くことも可能です。自分にとって理想的な方法を見つけてくださいね。
絵本のタイトルを決める
絵本の制作が完了したら、次はタイトルを考えましょう。
タイトルは、物語のキーワードや印象に残るフレーズから選ぶと良いです。キーワードとしては、主要な登場人物や物の名前を使用するのが一般的です。
たとえば、先ほどの物語が「ケーキ」と「リス」と「うさぎ」と「クマ」と「森の動物たち」を中心に展開されていた場合、「森のケーキ」というタイトルが考えられます。
物語が森で展開される場合、タイトルに「森の」を付け加えることで、シリーズ化しやすくなります。例えば、「森の冒険」や「森の生活」といった形でシリーズを拡張できます。
タイトルを考える際には、「短くて覚えやすい」を心がけると良いでしょう。
まとめ|幼児向け絵本づくりのアイデアと構成を押さえて楽しく制作!
絵本づくりは、テーマとストーリーの型を押さえるだけでスムーズに進められます。
この記事では、「幼児向け絵本 ストーリー 例」を軸に、実際のストーリー例やテンプレートも紹介しました。
以下の比較表を参考に、自分に合ったスタイルを見つけてみてください。
| テンプレ名 | 主なテーマ | 難易度 | こんなときにおすすめ |
|---|---|---|---|
| キャラ×困りごと×解決 | 日常・冒険 | ★☆☆ | 初めて絵本を作るときにおすすめ |
| もし◯◯だったら? | 空想・発見 | ★★☆ | 想像力を伸ばすお話にしたいとき |
| 季節×ハプニング | 行事・共感 | ★★☆ | 季節感や行事を取り入れたいとき |
| 数・色リズム型 | 知育・音遊び | ★☆☆ | リズム感や言葉遊びを楽しませたいとき |
| 感情 | 気持ち・共感 | ★★☆ | 子どもの気持ちに寄り添いたいとき |


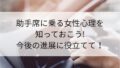
コメント