産休前、有給休暇を「どのくらい残すべきか」「それとも使い切るべきか」で悩んでいませんか?
同僚に聞いてもバラバラ、ネットの情報もいまいちピンとこない…そんな方のために、この記事では以下のような内容をわかりやすく解説します。
この記事では…
・産休前に有給をどのくらい残す?使い切る?
・産休前の有給休暇の適切な取り方
・産休開始時に残る有給休暇の処理方法
などをお話していきます。
あなたの状況に合わせて、納得できる判断ができるよう、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
現状把握から始めよう!

まず、保有する有給休暇の現在の日数を把握し、そのままにしておいた場合、復帰後にどれだけの休暇が消失する可能性があるかを調べましょう。
有給休暇の基礎知識
会社の就業規則を確認してみてください。
記載がなくても、労働基準法でこのように定められていますので、勤務していない間に有給休暇が得られないということはありません。
有給休暇の最大保有期間を確認しましょう。
労働基準法では最長2年間ですが、会社によってはそれ以上の期間を設定している場合もありますよ!
現在の有給休暇の残日数の確認
これは会社ごとに異なりますが、勤怠管理システムで確認ができたり、それが難しい場合は総務部に確認するなりしましょう。
自分がどれだけの有給休暇を利用できるかを把握する!
有給付与日と付与日数の確認
就業規則を確認して、有給休暇の付与日と付与される日数を把握します。
●有休付与日
会社や入社月によって異なりますが、4月に一律、決算日翌日に一律などルールがあります。
●有休付与日数
勤続年数によって異なりますが、長く勤めるほど、通常は年間最大20日が付与されることが多いです。
復帰時の有給休暇の見込み
現在の有給休暇の日数が1年後の育児休暇復帰時にどう変わっているか、どのような消失があるかを調査しましょう。
使用すべき日数の検討
例えば、現在30日の有給休暇を持っていて、4月に1日付与される場合、1年後に復帰すると仮定すると、20日を繰り越せるため、10日が消滅します。
(ただ、保育園の関係ほか、復帰できる・復帰するタイミングは状況次第です)
少なくとも消滅する分は使い切るべきですが、次の付与月次第で、全部使い切る選択肢も考えられます。
自分の状況に応じて、使うべき日数や残すべき日数を計画的に決めましょう。
産休前に有給をどれくらい残す?使い切る?

産休に入る前に使う有給休暇の計画が立てられたら、消滅する可能性がある休暇は前もって使い切ることが最も効率的です。
たとえば、10日分の有給休暇が残っている場合、実質的には約2週間前に産休を開始することができます。
このアプローチにより、無駄なく休暇を利用することが可能になります。
産休入りする前に必要な業務の引継ぎを計画的に進めましょう。
産休前に有給を使い切る?残す?判断に迷ったときの考え方
「全部使い切る」が向いているケース
- 有給休暇の残日数が多く、近い将来に消滅する可能性がある場合。
- 業務の引き継ぎが計画的に進んでいて、休暇前の準備も完了している場合。
- 心身のゆとりを持って出産準備を進めたい、また生活リズムを整えておきたいと考えている場合。
- 復帰後にまとまった休みを取りづらい部署や業種で働いている場合。
- 有給休暇を使えるタイミングが限られていて、今を逃すと消化しにくい状況にある場合。
こうしたケースでは、有給休暇を「前倒しで計画的に使い切る」判断がしやすくなります。
特に、出産前に落ち着いた期間を確保したい方にとっては、有給の一括使用がとても現実的な選択肢といえるでしょう。
「少し残しておく」が向いているケース
- 復帰後の生活や勤務スタイルに不安があるため、柔軟に対応できる余地を残しておきたいと考えている場合。
- 部署の人手不足や繁忙期などの事情があり、すべての有給を取得しきれない可能性がある場合。
- 育児と仕事の両立を見越して、突発的な出来事にも備えておきたいという考えがある場合。
- 復職直後に少しずつ勤務時間を調整しながら慣れていくスタイルを希望している場合。
このように、有給休暇をすべて使い切るのではなく「数日残す」という判断にも十分なメリットがあります。
状況に応じて、無理なく働き方に幅をもたせられる点が魅力です(会社の就業規則をご確認ください)。
決め手は「現状の把握」と「職場環境のバランス」
どちらを選ぶべきかを決める際には、以下のようなポイントをチェックしておきましょう。
- 現在の有給残日数と取得期限
- 次の有給付与のタイミング
- 有給休暇が消滅する見込みがあるかどうか
- 所属部署の人員体制や繁忙状況
- 上司や同僚とのコミュニケーションの取りやすさ
こうした情報をもとに、「使い切る/残す」それぞれのシミュレーションをしてみると、自分に合った選択が見えやすくなります。
制度としてのルールや権利はあっても、実際には会社の文化や部署の雰囲気など、目に見えない要素も大きく影響します。
大切なのは、自分自身が納得できるかどうか。
そのためにも、数字だけではなく、周囲との関係性や復帰後の働き方にも目を向けながら、バランスの取れた判断を心がけましょう。
産前休業を有給休暇で賢くカバー?

産前6週間に迫った状況で業務が未完了である場合、特に引き継ぎが間に合わないときは、有給休暇の消滅を避けるための策を講じましょう。
産前休業の柔軟な取得
産前休業は、出産予定日の6週間前から取得可能ですが、必ずしも取得しなければならないわけではありません。
実際には、産前休業に入ることなく、有給休暇を使って休むという方法もあります。
出産手当金と有給休暇の比較
出産手当金は通常、給料(残業代を含む)のざっくり2/3ですが、この金額と基本給を比較すると、多くの場合、基本給の方が高くなります。
非常に多くの残業をしている人を除いて、通常は有給休暇を優先すべきです。
産前休業を有給休暇で置き換える戦略
有給休暇の方が金銭的に得する場合は、産前休業の開始を遅らせ、有給休暇でカバーするのが賢い選択かもしれません。
これにより、出産手当金の額は減少しますが、その分有給休暇を活用することで損失を最小限に抑えられます。
産休中は社会保険料が免除されますが、有給休暇でも同様の扱いを受けることができます。
さらに、賞与などの計算においても有給休暇の取得タイミングを適切に調整することが重要です。
産休前の有給休暇、みんなはどうしてる?【リアルな声】

ケース①:復帰後のために数日残したAさん
「全部使ってしまうつもりでしたが、復帰後の調整がしやすいように5日だけ残しました。 実際に保育園の慣らし期間で使えてよかったです。 いざというときに有給が残っているというだけで、気持ちにも少し余裕ができましたし、 子どもの急な予定にも落ち着いて対応できました」
→ 復帰後の予定や生活にあわせて、柔軟に考えたパターンです。
今だけでなく、「その後」を見越して判断する視点が印象的ですね。
ケース②:キリのいいところで一気に使い切ったBさん
「引き継ぎも終わっていたので、産休前の2週間を有給で過ごしました。 おかげで心身ともにゆとりができました。 最後の出勤日から少し余裕を持って休みに入ることで、バタバタせずに準備も整い、 落ち着いた状態で出産に向き合うことができたと思います」
→ 計画的に準備が整っていれば、有給を使い切るという選択もしやすくなります。
事前の段取りと周囲との連携があれば、よりスムーズに有給を活用できる良い例です。
ケース③:部署の事情を見て調整したCさん
「部署が忙しい時期だったので、全部は使わず半分だけ使って産前休業に入りました。 業務のタイミングとチームの状況を見ながら、無理なく引き継げるように日程を調整しました。 その分、復帰後もスムーズに戻りやすかった気がしますし、周囲からのサポートも得られやすかったです」
→ 職場への配慮も含めて、全体のバランスで判断した例です。
「自分のため」だけでなく「周囲との関係性」にも目を向けた、実践的な選択といえるでしょう。
人それぞれ、「正解」はひとつじゃない
どの選択が正解ということはなく、自分の働き方や価値観、そして会社の状況に応じて柔軟に考えることが大切です。
実際にどのように取得するかは、個々の事情やライフスタイルによって異なります。
有給休暇の残し方・使い方に迷ったときは、今回ご紹介したような事例をヒントに、 「自分にとって心地よい選択」ができるよう整理してみるとよいかもしれません。
焦らず、落ち着いて判断することが、結果的に満足度の高い働き方につながります。
まとめ
産休を控えた方々にとって、有給休暇の管理は非常に重要です。
この記事では、産休前に有給休暇を最大限に活用する方法について解説しました。
特に、有給休暇が消滅する可能性がある場合、産前にこれを利用して早めに休暇に入ることが、無駄を防ぐための賢い戦略となります。
産前休業と有給休暇の使い方を適切に計画することで、金銭的な損失も最小限に抑えることが可能です。
また、産前休業を有給休暇でカバーする選択肢もあり、これにより出産手当金の減少を補うことができます。
産休を迎える前のこの貴重な時期に、有給休暇の残日数をしっかり管理し、自身の状況に最適な休暇の取り方を検討しましょう。
これにより、産休中も安心して過ごせるだけでなく、復帰後の職場復帰もスムーズに行えるでしょう!

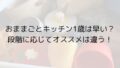
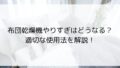
コメント